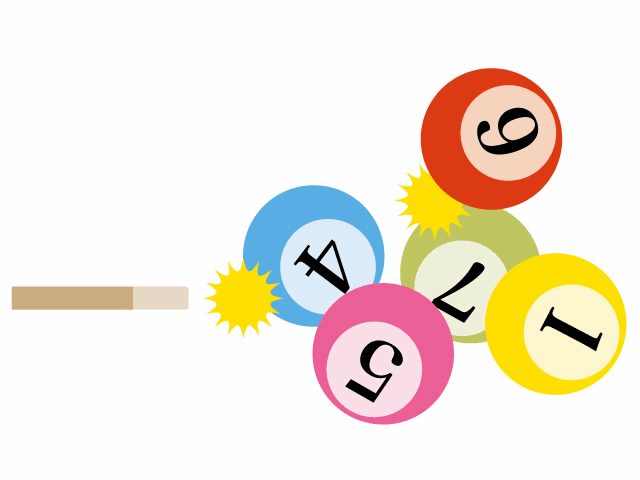
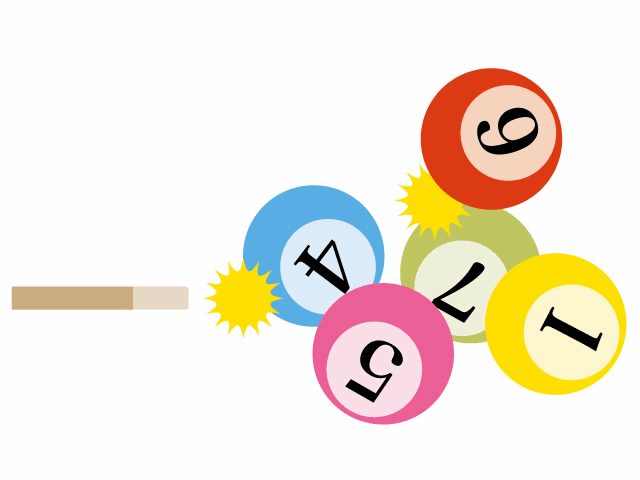
![]()
4 原告らの損害は戦争損害であり、憲法の枠外の損害であって違憲違法と評価される余地はないこと
(1) 前記第2でも述べたとおり、原告らの主張する損害は、戦争被害ないし戦争損害として、国民等しく受忍しなければならなかったものである。この点に関する前掲最高裁判所昭和62年6月26日第二小法廷判決を改めて詳しくみると、主張して国賠法1条1項に基づき損害賠償請求した本件と同種の事案について、「戦争損害ないし戦争損害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民等しく受忍しなければならなかったところであって、これに対する補償は憲法の全く予想しないところというべきであり、したがって、右のような戦争犠牲ないし戦争損害に対しては単に政策的見地からの配慮が考えられるに過ぎないもの、すなわち、その補償のために適宜の立法措置を講ずるか否かは国会の裁量的権限に委ねられるものと解すべきことは、当裁判所の趣旨に徴し明らかというべきである(昭和40年(オ)第417号同43年11月27日大法廷判決・民集22巻12号2808頁参照)。そうすると、上告人らの前記主張に沿う立法をしなかった国会ないし国会議員の立法不作為につき、これが前示の例外的場合に当たると解すべき余地はないものというべきであるから、結局、右立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。また、上告人らは前記主張にそう法律案を国会に発案しなかった歴代内閣総理大臣及び国務大臣の不作為をも違法であると主張し、右主張は歴代内閣の前記法律案不提出についても、同条項の適用上違法性を観念する余地のないことは当然というべきである。」と判示して、立法不作為及び行政不作為に基づく請求を認めなかった。
(2) ところで、上記最高裁判決のいう「戦争損害」とは、「一般的には、軍人・軍属として戦場における戦闘行為等に参加することにより不可壁的に発生する生命侵害や身体の損傷、私有財産等の喪失のほか、戦闘行為には直接参加しなかったものの、一般国民が敵国軍の焦土作戦に基づく空襲や砲撃等の擬制になった死亡したり、重大な傷害を受け、あるいは個人所有の家屋敷や家財道具等を焼失・奪取されることに伴う各般の戦災等を指称」するとされている(東京高等裁判所平成5年3月5日判決・シベリア長期抑留等補償請求事件控訴審判決)。 本件訴訟における原告らの請求は、要するに先の大戦によって国民に生じた諸々の被害及び損害のうち、原告ら東京大空襲の被害者及びその遺族に生じた損害について、国に「賠償」ないし「補償」という形で救済するように主張するものであるから、その主張する損害が戦争損害に該当することはあきらかである。
(3) したがって、原告らの受けた損害は憲法の枠外の損害であって、それを賠償ないし補償しないという立法ないし行政上の不作為が、国賠法上違法であると評価される余地はない。
この点からも、原告らの請求及び主張は失当である。
第5 結語 へ
▸目次の 第4-4 を検討します
▼ 4 原告らの損害は戦争損害であり、憲法の枠外の損害であって違憲違法と評価される余地はないこと
冒頭の「戦争被害ないし戦争損害として、国民等しく受忍しなければならなかったものである。」 とは?! 憲法が保障する国民の基本的人権を、無視、あるいは軽視する旧官僚的思惑は、あまりにも言語道断に過ぎて意味不明である。
空襲等で被害を受けた国民は、現憲法の下で援護を求めている。ところが「憲法の全く予想しないところ」という。戦争被害や戦争損害を救済・援護する一意的条項が憲法にないからか。公僕たる高級公務員の言ではない。憲法に一意的条文が無ければ、下級法で立法化することが政府と国会の責務であろう。
憲法は、第11,12,13,14,16,17,29条などを控えている。特に13条、29条は重要である。これを一意的に具体化して立法化すればよい。行政と国会は毎年たくさんの福祉的法律をつくったり、改正している。
▼ この訟務局答弁書の半ばで、空襲被害者等の援護請求や賠償請求は、その補償のために適宜の立法措置を講ずるか否かは国会の裁量的権限に委ねられるものと解すべきとし、敢えて時代錯誤の昭和43年の「国外資産喪失至急事件」の判例を持ち出している。
戦争被害者に対する援護法の立法措置は、憲法に照らして、国会の裁量的権限というよりも義務的権限である。
同様に行政の義務的権限なのである。同じ憲法の下に軍人・軍属に対する国家的補償がなされている。
現実は、重要な責務を持っていながら、国の行政に関わる公務員・特別職が、長期にわたって空襲等被害者等国民の悲惨な状況を無視し、憲法の人権に関する条項を鑑みなかった、あるいは故意に見逃してきたことは、結果として下記国賠法の適用に値する。
国賠法は、まさに憲法第17条の基に、この場合のための法律としてつくられている。
国家賠償法
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
行政による努力義務の怠慢ばかりか、故意に憲法違反を犯した例を三つ挙げる。
一つ、1973(昭和48)年の第48回国会から1988(昭和63)年の第63回国会まで、「戦時災害援護法案」が14回参議院に提出されたが、すべて審議未了(別紙資料)。
二つ、1979(昭和54)年6月、厚生相だった橋本龍太郎氏の諮問機関に「原爆被爆者対策基本問題懇談会」が設置された。最高裁が78年3月、被爆者援護法の前身にあたる原爆医療法について「実質的に国家補償的配慮が制度の根底にある」と指摘したことを受け、大学教授や元最高裁判事ら7人の委員が議論。80年12月にまとめた「原爆被爆者対策基本問題懇談会答申書」は、原爆放射線被害による健康被害は「特別な犠牲」として援護するが、それ以外の戦争被害は「一般の犠牲」と位置づけ、すべての国民がひとしく受忍しなければならないものとした。
三つ、1984(昭和59)年1月21日、平和祈念事業特別基金を創設するための総理府総務長官の諮問機関による、「戦後処置問題懇談会」が設置された。
その第1回懇談会は1982年6月30日。最初の議題は、未解決の「戦後処理問題」の範囲をどう定めるか。田辺圀男・総務長官が、設置の経緯の中で、「先の大戦に関しましては、すべての国民が程度の差こそあれ、戦争による何らかの犠牲を余儀なくされたということであります。このような戦争被害につきましては、これを完全に償うことは実際上不可能でありまして、国民の一人一人に、それぞれの立場で受けとめていただかなければならないものと考えておるわけでございます」などと述べている。
この報告書の別添書の冒頭で、
「1 およそ戦争は、国民すべてに対して何らかの損害を与えるものであり、全国民がその意味で戦争被害者といえるもではあるが、その中で、戦後処理問題とは、戦争損害を国民の納得を得られる程度において公平化するため国がいかなる措置をとるかという問題である。
政府はこれまで、その段階、段階に応じて戦後処理を行ってきたところであり、その結果、昭和42年、在外財産問題の決着を以って戦後処理は一切終結したことを政府与党間において了解したところである。」
この懇談会の準備会合で、「外務省として、懇談会で取り上げ検討することすら、全て反対」(外務省課長)、「パンドラの箱をグッと占める方向に持っていきたい」(内閣審議室長)などの発言があった。会議はそうした官僚のお膳立てに進んでいったという。
以上、永い期間の参議院審議と、二つの懇談会報告は、憲法を無視し、民間戦争被害者を救済から除外した証拠、完全に故意による行政不作為の証拠である。
▼(2)の上半で、「戦争損害」を指称して、軍人・軍属と一般国民の双方を戦争損害であることを認めている。
にもかかわらず、後半で「要するに先の大戦によって国民に生じた諸々の被害及び損害のうち、原告ら東京大空襲の被害者及びその遺族に生じた損害について、国に「賠償」ないし「補償」という形で救済するように主張するものであるから、その主張する損害が戦争損害に該当することはあきらかである。」とは、文脈が捻じれているようだ。
冒頭と同じく、答弁書に大きな論理的矛盾があるために意味不明。
戦争に因る損害ではないと言えば、救済に該当するというのか。空襲被害者が、「空襲ではなく、一般の事故による被害であるとか、地震・台風など自然災害によるものである」などと自分の実人生を偽るわけにはいかないか。
1951年の「戦傷病者戦没者遺族等援護法」と、翌年の「軍人恩給法」復活の憲法上の根拠は何なのだろう。「軍人恩給法」が対象としている軍人の社会階級は、戦後は憲法14条でなくなっている。
へ
第5 結 語